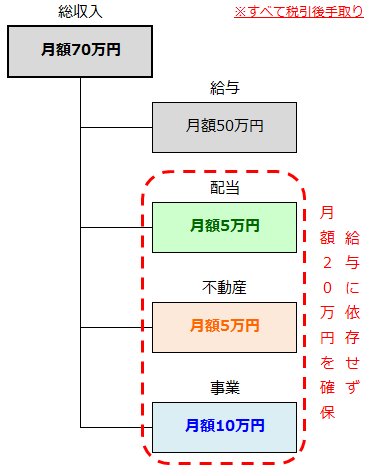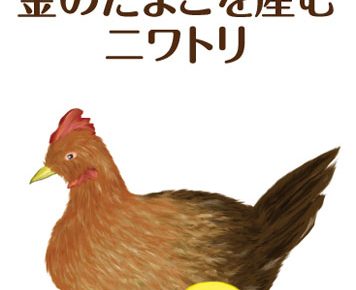簿記3級をクリアして、2級の勉強をはじめると出てくる「工業簿記」。初めて学ぶ分野ですから、気になることがたくさんありますよね。
そんな人のために、商業簿記と工業簿記についてまとめます!
私こびと株は、
- 簿記歴15年超
- 経理歴10年超
- 簿記1級ホルダー
なので、簿記にはちょっと、詳しいですよ~!
商業簿記と工業簿記は、結構違います。

どちらかが苦手になりがちな、商業簿記と工業簿記ですが、捨て科目を作ると
- 試験に受かるのが難しくなる
- 仕事で使うときはメッチャ困る
というデメリットが…。
ぜひ、両方ともきちんと理解して、簿記を使いこなせるようになってください!

※資料を請求すると、無料でサンプル教材がもらえます。見てから決めればOKなので、とりあえず請求だけしておきましょう。
目次
商業簿記と工業簿記、違いは何?

一言でまとめるなら、
- 商業簿記は、商品売買業を対象とした簿記
- 工業簿記は、製造業を対象とした簿記
ということになります。
日商簿記検定の2級でいえば…
商業簿記は3級で学んだことの延長です。
- 本支店会計
- 連結会計
- リース
- 外貨建取引
など、より複雑でより実践的な内容が出てきます。

一方工業簿記は、簿記2級ではじめて出てきます。製造業に特有の取引を取り扱うことになります。
製造業の特徴は、製品を製造すること。
- 材料を仕入れて
- 人や機械が加工して…
といった過程があります。
このような過程で、製品の製造にいくらかかったのかを計算し(「原価計算」といいます)、その結果を簿記のルールに従って記帳していく…。これが、工業簿記なのです。

(参考:「スッキリわかる 日商簿記2級 工業簿記 第10版[テキスト&問題集]」)
商業簿記と工業簿記、難しいのはどっち?

商業簿記と工業簿記の難易度については、人によってずいぶん感想が違います。
ざっくりいうと、
- 国語嫌い:難しいのは商業簿記!
- 算数嫌い:難しいのは工業簿記!
という傾向にあるようですね。
商業簿記を理解するためには、会計のルールをひとつずつ覚えていかなくてはいけません。そのためには、少々ややこしい文章を読み解かなければならないこともあります。
このあたりが、国語嫌いさんに「商業簿記は難しい…」と思わせてしまうポイントかと思われます。
一方工業簿記では、たくさんの計算が必要とされます。特に原価計算では、足し算・引き算・かけ算・割り算を駆使して、製品の製造原価を求める必要があります。
計算方法も、暗記というよりは考え方の理解が重要です。
このあたりが、算数嫌いさんにとってはなかなかやっかいなポイントになるでしょう。

商業簿記と工業簿記、学ぶ順番はどうすればいい?

「すぐに経理実務で使いたい!」という人が、先に学ぶべきは商業簿記です。
商業簿記の方が、広く一般的な取引を扱っているからです。
「とりあえず簿記2級(もしくは1級)をとろう!」という人は、
- 商業簿記の基礎
- 工業簿記
- 商業簿記の応用
という順番で学ぶのが◎です。
商業簿記と工業簿記を比べると、
- 商業簿記:暗記要素が多い
- 工業簿記:計算方法を理解していればOK
という傾向があります。(相対的な傾向です。)
試験対策という意味では、暗記要素の多い商業簿記は直前期に取り組みたいもの。せっかく覚えたことを、忘れてしまっては元も子もないからです。

しかしその一方で、簿記の知識ゼロから工業簿記に手を付けるのはおすすめできません。商業簿記の基礎がないと、工業簿記の内容も理解にしにくいからです。
まずは商業簿記の基礎を学んで
- 仕分けって何?
- 貸借って?
- 減価償却費…???
みたいなレベルを脱出しましょう。帳簿の見方がざっとわかるようになってから、工業簿記をはじめるのがおすすめです。

…というわけで、商業簿記と工業簿記の勉強順序は
- 商業簿記の基礎
- 工業簿記
- 商業簿記の応用
が良いのです!
商業簿記と工業簿記、それぞれ使うべき教材は?

基本的には、個別教材を探すより、資格スクールを利用した方が良いと思います。
- 独学は、つまずきやすい
- 独学は、理解が不十分なことが多い
のがその理由です。

具体的には、クレアールを使うと良いでしょう。コスパ最強なので、圧倒的におすすめです。
科学的に解析され、厳選された超効率的な学習法で
- 効率重視で合格したい
- 忙しくて時間がない
- 費用を抑えて取り組みたい
という人に向いています。
WEB通信での学習が基本なので、スマホ学習でスキマ時間を活用できますし、早見再生で時間短縮もできます。音声のみのデータも用意されています。
こういうちょっとした利便性が、合格と挫折を分けたりするのですよね。
※資料を請求すると、無料でサンプル教材がもらえます。見てから決めればOKなので、とりあえず請求だけしておきましょう。
念のため、「どうしても独学したい!」という場合のおすすめテキスト&問題集もまとめておきます。
商業簿記も工業簿記も、変わらず「スッキリわかる」シリーズです。
商業簿記・工業簿記ともに、とてもわかりやすく解説されている、大人気のシリーズ。大手資格スクールTACが出版しているところも、安心要素ですね。
Amazonのページに飛ぶと、「なか見!検索」で内容を確認できるので、ぜひチェックしてみてください。
ちなみに、過去問題集は、収録年数の多いものを選ぶことが重要です。試験勉強のポイントはとにかく手を動かすことだからです。
↑こちらは、12回分と大容量でオトクなのでおすすめです!
商業簿記と工業簿記、勉強するとき注意すべきポイントは?

- 商業簿記:ルールを覚えること
- 工業簿記:考え方を理解すること
これがそれぞれの分野で、注意すべきポイントです。
商業簿記で「理解」を優先しすぎると、いつまでたっても試験勉強が終わらないワナにハマります。
一方、工業簿記で暗記に偏った学習をすると、ちょっとひねった問題はさっぱり解けないというワナにハマります。

ちなみに、商業簿記・工業簿記共通のポイントは「とにかく手を動かすこと」です。
テキストを読んで、問題集の解き方解説を眺めて、勉強した「つもり」にならないように注意しましょう。

商業簿記と工業簿記、苦手な人はどうすべき?

商業簿記と工業簿記、同じ「簿記」とは言っても、ずいぶん違った特徴をもっていますよね。
ですから

とか

とか、感じる人は少なくありません。
こういう人も、ひとりでもがくのは止めにして資格スクールを活用すると、学習がスムーズになります。スクールの講師は、簿記を教えるプロだからです。
苦手分野に心が折れてしまう前に、彼らの解説を聞いてみましょう。独学との理解度の違いに、びっくりすること請け合いです。

商業簿記と工業簿記、片方捨てても試験に受かる?

苦手科目がある人が、考えがちなのがコレ。「苦手科目は捨てて、得意科目だけ頑張れば試験に受かったりしないかな?」ということです。
結論から言うと、それはなかなか難しいです。
例えば、簿記2級。
合格には「70%以上」の得点が必要です。配点は、商業簿記60点、工業簿記40点。
つまり、合格のためには
- 商業簿記が満点でも、工業簿記で25%
- 工業簿記が満点でも、商業簿記で50%
は得点が必要ということになります。
また、簿記1級の合格基準には、「1科目ごとの得点は40%以上」という制限がつけられています。合計点が高くても、全然ダメな科目が1つでもあると受からない、という仕組みなのです。

ちなみに私こびと株自身は、簿記1級合格時、ものすごく偏った点数をとりました。
- 商業簿記&会計学 :得点率40%
- 工業簿記&原価計算:得点率100%
みたいな感じで…。全体での得点率も70%(合格基準)ギリギリでしたし、商業簿記&会計学の得点率は40%(科目別足切り)ギリギリでした。
いえ、これでも私、商業簿記と会計学の勉強、かなりがんばったですよ?がんばったけど全然わからなくて…ヤマが当たったタイミングで受かったというか…。
捨て科目ができると、試験全体が運試し状態になりかねません。ぜひ、バランスよく勉強しましょう。

簿記を学ぶ目的が「とりあえず試験に受かりたい!」だけであれば、捨て科目を作るのも場合によってはアリかもしれません。
捨て科目があっても運が良ければ受かりますから、回数を重ねればいつかは合格できる(と思われる)からです。

でも、簿記を仕事に活かしたいと思っているあなた!あなたは、絶対に捨て科目を作ってはいけません!
仕事で担当になったときに「あ~私、その科目は捨ててたからわかんないんです♪」では済まされないからです。
「商業簿記苦手…」とか「工業簿記わかんない…」とか思ったら、独学はあきらめてスクールに通いましょう。結局、それが一番効率的です。

簿記を仕事で使うなら、捨て科目は作っちゃダメです!就職後に後悔しないためにも、ぜひ全体的な理解を深めてください。
まとめ:商業簿記と工業簿記

商業簿記と工業簿記は、結構違います。

どちらかが苦手になりがちな、商業簿記と工業簿記ですが、捨て科目を作ると
- 試験に受かるのが難しくなる
- 仕事で使うときはメッチャ困る
というデメリットが…。

それではまたっ!
※関連記事です
Follow @kobito_kabu