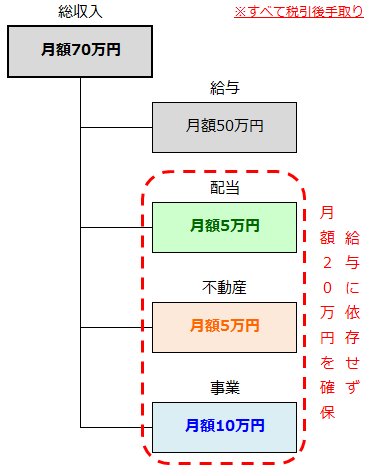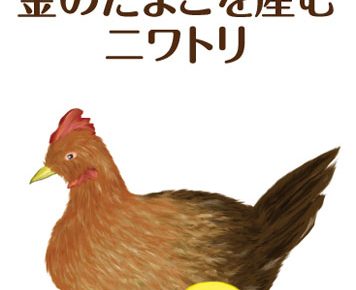こんな人の為の記事です。
経理の資格と言えば、簿記!
会計の最高峰資格と言えば、公認会計士!
そんな会計の世界で働く経理マンが、あえて「証券アナリスト」という資格を取るメリットについて考えてみました。
他の経理マンとの差別化を図りたい方、経理・財務・IRの仕事に興味がある学生さんは是非ご覧下さいませ。

目次
そもそも証券アナリストって?

証券アナリストとは
証券アナリストとは、証券投資の分野において、高度の専門知識と分析技術を応用し、各種情報の分析と投資価値の評価を行い、投資助言や投資管理サービスを提供するプロフェッショナルです。
(出典:日本証券アナリスト協会)


でも、確かに説明するのは難しそうです。
なぜなら、証券アナリストというのは法律で定められた資格ではなく、民間団体の認定資格にすぎないからです。
実は、資格を持っていなくても誰でも「アナリスト」を名乗れるし、「アナリストの仕事」ができるのですね。弁護士や公認会計士のような独占業務はありません。
具体的に見てみると、証券アナリストとは次のような人達です。
- 証券会社で、企業や業界の分析をして株式の評価をする人(リサーチアナリスト)
- 銀行や保険会社で、株式や債券などのポートフォリオを運用する人(ファンドマネージャー)
- 投資銀行や投資顧問で、企業や業界の分析をしてミクロ・マクロレベルで投資戦略を決定する人(投資ストラテジスト)
証券アナリストの人数は?
2022年9月時点で、28,304名の証券アナリストがいます。
普通の事業会社で働いている人は16%しかいません。

どんな試験勉強をしてアナリストになるの?
この6分野です。
- 証券分析とポートフォリオ・マネジメント
- 財務分析
- コーポレートファイナンス
- 市場と経済の分析
- 数量分析と確率・統計
- 職業倫理・行為基準(アナリストとして順守すべきルール)
受験するには、証券アナリスト協会の通信教育を受講して、一次試験・二次試験を突破する必要があります。制度上、最低でも2年間の勉強が必要になる資格です。

経理マンが証券アナリストを取得するメリット

IR部門への異動・転職がしやすい
インベスター・リレーションズ(Investor Relations、IR)とは、企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信する活動をいう。
(出典:wikipedia)
IR担当者は、企業の窓口となって外部のアナリストからの質問に回答する必要があります。
でもそれが非常に難しいのですね。なぜなら、IR部門で働いている人は、そもそも会計やファイナンスの専門家ではないからです。
うちの会社でも、IR担当者から経理部に、

っていうお願いがよくきていました。
さて、このIRの仕事、世間では割と人気のある職種だと思います。異動したくても、結構競争率が高いのではないでしょうか。
経理経験者であるというだけで、他部門の希望者に比べると有利かも知れませんが、証券アナリストの資格を持っていればまず他の希望者には負けないと思います。

管理会計の業務に就きやすい
これはもう単純にイメージの問題ですが、一般に「アナリスト=分析が得意」なイメージが定着しています。
なので会社内で「管理会計分野の仕事がしたい!」というアピールをする時にも有利です。
実際、私は証券アナリスト1次試験に合格しただけで管理会計系のグループに異動することができました。

他の経理部員との差別化がしやすく、生き残りに有利
ある程度の企業規模になると、日商簿記1級を持っている人はゴロゴロいるので、日商簿記1級をとってもアピール材料になりません。
中には公認会計士や税理士などの資格を持っている人もいるので、簿記の資格だけではますます太刀打ちできなくなっていきます。
しかし、証券アナリストの有資格者はほとんどいません。
- 公認会計士は監査のプロ
- 税理士は税法のプロ
- 証券アナリストは企業・産業分析のプロ
といった具合に、分野が被らないのでとても差別化がしやすいです。
簿記+証券アナリストの組み合わせは、非常に分かりやすい差別化だと思います。
財務諸表を作るのも分析するのも得意な人、というイメージを持ってもらえるでしょう。
こういった差別化は、サラリーマンの生存戦略としては非常に重要ではないでしょうか。

まとめ

経理マンが証券アナリストの資格を取るメリットをまとめます。
- IR部門への異動・転職がしやすい
- 管理会計の業務に就きやすい
- 他の経理部員との差別化がしやすく、生き残りに有利
簿記+証券アナリストは、経理部門ではレアな人材になれる!ってことですね。
間違いなく担当業務の幅・視野は広がると思うので、勉強して損はないと思います。
ただし年収に直結するかというと、それはないと思いますが。残念ながら。
年収を上げることが目的の場合は、資格取得+転職がいちばん手っ取り早いです。
私も証券アナリスト学習中に転職活動をした際、
- ベンチャー企業のCFOから評価されたり
- 転職エージェントから評価されて財務系の案件を紹介されたり
学習中というだけでも割とメリットを感じました。この辺、ネット上だと少し過小評価されている気もします。
いくつか転職エージェントを利用しましたが、年収上げたい経理マンにおすすめしたいのはJACリクルートメントですかね。
ハイクラス・専門職向けで外資系に強いエージェントですが、日系大手の案件も意外と多いエージェントです。利用無料なので登録しておいて損はないです。
証券アナリストの資格を取得する意味があるかどうか悩んでるなら、
「自分にとって、証券アナリストは取得すると転職に効果があるか」
早いところ転職エージェントに相談してしまった方がいいと思います。現職や年齢などによって回答が変わるでしょうから、直接確認してしまうのが一番効率的で合理的です。
役に立たなそうなら、コスパの悪い投資(学習)は辞めておきましょう。一方で、もし取得するメリットを感じられたらチャレンジしてみるのは悪くないと思います。
需要を確認してから勉強するのが資格試験の鉄則です。

それでは!
※関連記事です
合格ノウハウをすべて詰め込んだ記事を作成しました!
Follow @kobito_kabu